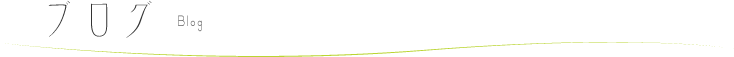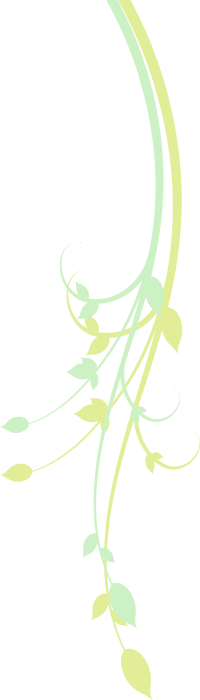4月6日の一夜漬けのような試験に落ちて考えました。まず、受験日を決めよう!熱が冷めないうちが良い。でも何と今から最も忙しい3月決算(5月申告)が始まる。あまり無茶な設定だと受験料も勿体ないので、約2か月後の6月9日に設定しました。一度受けて一夜漬けではダメだと悟ったので、ちゃんと勉強しようと決意して、まず、勉強時間の確保から始めます。5月末までは仕事の繁忙期なので仕事時間は削れない。けれど週末の予定もすでにすべて入ってしまっている。さて、どうしよう。ということで税理士試験の時もやっていた朝起きて1時間勉強を始めることにしました。
私は特に飛行機に乗るとか電車に乗って遠出をするという時でないかぎり目覚まし時計を設定しません。目覚まし時計の設定も念のためというか保険として行うので実質目覚まし時計なしの生活をしています。大体6時ころには目覚めるので6時から1時間勉強します。この1時間は、テキストをひたすら読むというもの。使用テキストは「いちばんやさしいITパスポート絶対合格の教科書令和6年度」と「ITパスポートかんたん合格教科書&必須問題」です。この本は1カ月で2回転づつ読みました。特にいちばんやさしい・・・の方はもともと15個くらいのカテゴリーに分かれているので毎日1つづつやるとちょうど15日で1回転するので1カ月で2回転します。カテゴリー毎にミニテストがついているので、それをやって終わりという感じです。間違えた問題については再と書いておいて合っていた問題には日付とOKと書きました。2回転目になると再と書いたものもできるようになっていて進展を感じます。
勉強にはインプットとアウトプットが大事です。インプットの時間7に対してアウトプット時間が3くらいの割合が良いと思っているので、仕事が終わると今度は事務所で「ITパスポート過去問題集」を解きます。これは過去問もありますが、3つのカテゴリー毎に問題が集中しているページもあり、まずは苦手なテクノロジからやりました。仕事の疲労度によってやる気やエネルギーが日々変わるので、最低1問解き、無理しないということを決めて始めました。勉強の一番高いハードルはやり始めるです。やり始めてしまえば1問といわず2~3問解けるのです。疲労度マックスの時は2~3問、エネルギーあるときは20問くらい解きました。こちらも間違えたら再と記載して解答説明文にマーカーや気づきなどを記載します。こちらも本試験までに2回転しました。
試験2週間前になると「ITパスポート過去問道場」というサイトで勉強を始めました。あまり古い試験日は試験内容が易しするので令和6年、令和5年、令和4年の他過去10年くらいのミックス問題を解いたりしました。1週間前には時間を図って2時間で解けるようにしました。この時点で700点から800点くらい取れるようになっていました。それから苦労した3文字単語(ローマ字3文字の用語の意義が山ほど出ます)の暗記はYouTubeの聞くだけITパスポートなどを沢山掲載されているので、それを活用しました。普段オーディブルで小説などを聞いている時間をこの単語の暗記時間にし、朝の支度時や通勤時間に聞きました。小説を聞けないのは残念だけど、6月9日までと我慢してひたすら聞きました。それでも間違う単語は単語帳のようなミニメモに記載して電車の中で見直しました。覚えやすいようにイメージやゴロなども記載して自分だけが分かる単語帳を作成しました。これが私の勉強方法です。忙しくても予定がパンパンでもやろうと思えば隙間時間を活用して勉強することができます。是非おためしあれ。