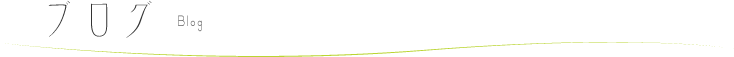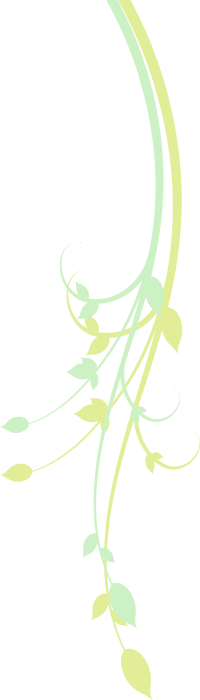最近お客様から、給付金・定額減税についてよく聞かれます。夏に電気代等が高騰し、岸田内閣が国民に補填すると発表しましたが、ちょっと難しくて良くわからない。結局低額所得者のみに給付されて私たちは関係ないの?という質問です。いやいや関係ありますよ。でも何段階にもなっているので複雑で分かりにくいだけです。順を追って説明します。
定額減税図解
図解を見ながら読んでほしいのですが、①まず、今年の2月~3月を目途に、低所得の子育て世帯に18歳未満一人につき5万円を加算します。
②住民税均等割りのみ課税世帯には1世帯10万円を給付します。
③そして住民税非課税世帯には1世帯7万円(自治体でも3万円を夏以降支援)を先行して給付します。
④①~③は令和6年度の住民税情報(令和5年の所得をベースにしている)を基に決定しているので、実際に令和6年に住民税非課税もしくは住民税均等割りのみ課税となる世帯には1世帯10万円を給付します。
とここまでは給付の話。これから減税の話になります。
住民税非課税や均等割りのみ課税の世帯以外の世帯は給付ではなく減税になります。給与所得者は、高額所得者(合計所得金額1805万円、給与収入だと2,000万円超)は減税の対象外になります。それ以外の方は今年の6月から給与の源泉所得税から減税されます。(給与の所得税の天引きが少なくなる)金額は、納税者及び配偶者を含めた扶養家族一人に付き3万円です。住民税は1万円になります。つまり、所得税などを払っている人は所得税3万円と住民税1万円の合計4万円が減税となります。扶養配偶者と子供2人がいれば、本人含めて4人なので4万円×4人の16万円が減税になります。6月の給与の天引きから考慮されますが、6月分の給与で充当できなかった場合は7月、8月、9月と繰り越して、12月まででも充当できなければ年末調整で考慮されます。ここまでが給与所得者の場合です。
次に、給与所得者ではなく、不動産所得者や事業所得者の場合は、予定納税対象者については第1回予定納税額から減税ですが、予定納税額がない場合等は確定申告で減税になります。減税額は給与所得者と同じです。(@一人4万円)
年金受給者はどうでしょう。年金受給者についても6月の年金から控除される源泉徴収税額から控除されます。6月に充当できない時は次回の8月(年金は2カ月に1度なので)に充当されます。年金受給者で源泉所得税がかからない人もいるかと思いますが、その場合は住民税非課税世帯もしくは住民税均等割りのみ課税世帯だと考えられるので前半にお話しした給付になります。
注意点としては住宅ローン控除がある人は住宅ローン税額控除後の所得税から減税を実施します。また年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、年末調整や確定申告で調整します。こちらの制度は様々な層の国民に丁寧に対応しながら、物価高に対応し、可処分所得を増やすことを目的としています。簡素・迅速・適切のバランスを考慮しているということですが、全然簡素じゃないですね。専門家でも複雑で説明が面倒なくらいです。今回給付と減税で対応が違うので複雑なのですね。本音を言えば6月から給与計算が大変になるな。給与ソフトはちゃんと対応してくれるのだろうか。と思っています。