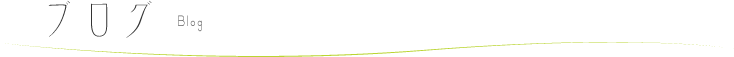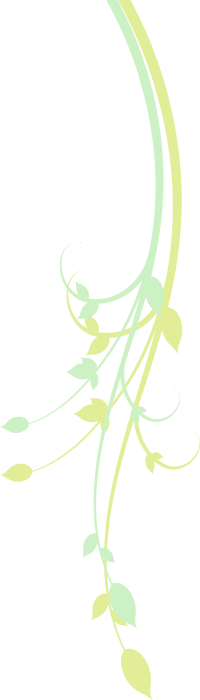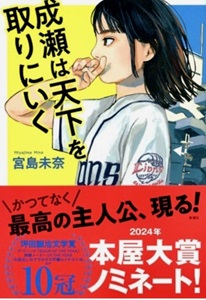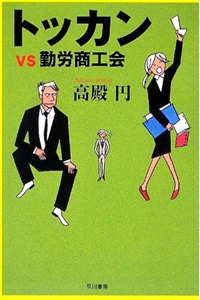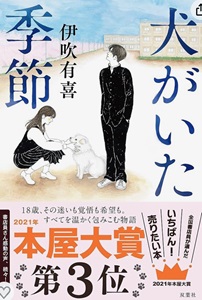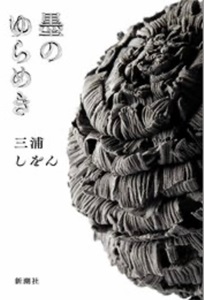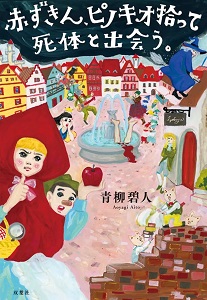再び科学系の本を読みました。大学に入ってからほぼ理科系は勉強していませんが、小学生から高校生までは一番成績が良かったのは理科だったので、やはり、私は生物とか科学とかに興味があるのだと思います。本の内容はかなり専門的ですが、歴史的変遷が軸となって話が展開します。その昔、人は人の中に入っていてそれが大きくなって生まれると、まるでマトリョーシカのように考えられていた時代から、メンデルがエンドウ豆の実験で有名なその遺伝子の基礎を発見し、メンデルの発見から遺伝子学が発展してきたようです。
その後、ワトソンとクリックがDNAは2本の鎖状のらせん階段のような構造だと発見しましたが、それにはフランクリンとウィルキンスの実験結果があったから実現したということで、この2人を協力者としてワトソンとクリックが発表しなかったのは、科学者として大いなる倫理違反であると痛烈に批判しています。フランクリンはX線構造科学者で結局X線を浴びすぎて卵巣がんになり亡くなってしまうという結末を迎えます。この部分の記述はこの本の中で唯一クレバーな著者が感情を強く出していて、私も共感しました。
DNAのその後の話はmRNA,tRNAと続き、科学者らしく、かなり専門的になりますが、遺伝子の歴史的変遷を知るには良本です。著者は研究者であり科学者なので面白さを追求しているというより専門書に近い本です。ちなみにメンデルの法則が有名になったのはメンデルが亡くなってからのようです。当時は発送がかっとんでいて誰も相手にしなかったそうな・・・