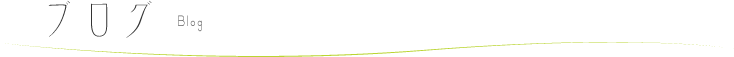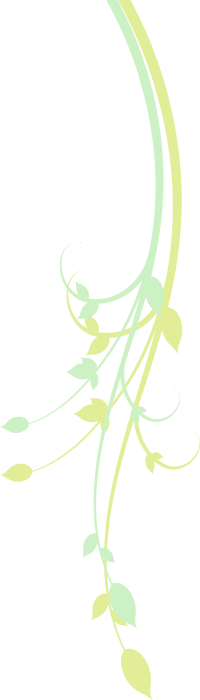DPC算定病棟に入院している患者が例えば眼科などの診療を受ける場合、入院している病院では眼科がなかったとします。そのような場合他の病院の診療を受けるのですが、眼科側で保険請求ができません。従ってその場合の費用は、入院している病院で患者に請求して、診療を受けた医療機関と入院している病院との間で合議によって請求します。合議とは話し合いですが、通常は行った診療が保険診療だったと仮定して点数に10円や11円を乗じて算定することが多いようです。この取り扱いについて、厚生労働省が事務連絡として通知しています。厚生労働省 事務連絡こちらの「DPC-26」ページのQ11-9 に下記の文章があります。
『問 11-9 DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要
となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機
関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等の
やむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る
費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報
酬の分配は、相互の合議に委ねるものとされているが、当該分配により他
医療機関が得た収入には消費税は課税されるか。
(答)健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消
費税法第6条)
質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療で
あるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け
取ったものについても非課税となる。(当該合議により得る収入については、
診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療
に係る診療報酬と同額である必要はない。』
えーこれ非課税なの?自費診療(消費税課税)じゃないの?保険証を忘れて自費診療になった場合は保険診療だったと仮定して診療点数に10円(もしくは10円×1.1)をかけた金額を自費として患者に請求します。でも医療機関同士の場合、ましてこのケースでは保険が使えないなら非課税でいいの?えー本当?厚生労働省が勝手に決めたんじゃなくてちゃんと財務省の承諾とっているの?患者と医療機関なら課税で医療機関同士なら非課税になるの?税務上は保険が使えれば非課税、保険が使えなければ課税だけれど、医療機関同士だと保険が使えなくても非課税なの?しかも説明の()書きに、合議により得る収入は・・・必ずしも他医療機関が行った診療に係る診療報酬と同額である必要はないって書いてあります。それでも非課税??
この取引は保険が使えない=消費税課税取引でしょ。非課税にしたいなら合理的理由(例えば合議であれば何でも良いのではなく、ちゃんと保険請求と一致した金額にするなど)が必要だと思うし、消費税法上も社会保険診療等は非課税とされていますが、社会保険診療報酬等でなくても社会保険請求したいけど入院中だからできないので社会保険診療報酬とみなす規定を作り金額も合意といった適当なものもOKとすべきではないと思います。それが法律だからです。なんじゃこれ!と思った通知でした。