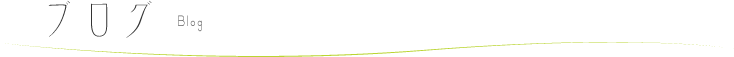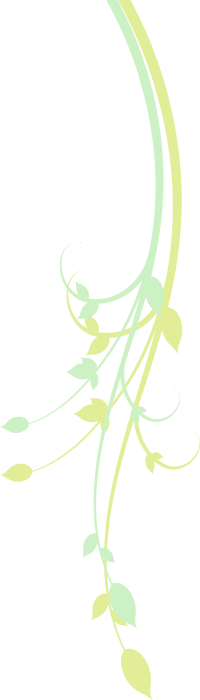コロナ禍から中小企業の借入金率が増えたような気がします。当事務所の顧問先様もコロナ前よりコロナ後の方が銀行借り入れをした企業が多くなっています。よく聞かれるのは「うちの会社はどのくらいまで借りられる?」という事です。以前は個人が住宅ローンを組む時にどのくらいなら借りられるかと聞かれたものですが、最近は会社ベースで聞かれることが多くなりました。そのような時、一般的に言われるのが債務償還年数です。これは企業がキャッシュフローで現在の借入金を何年で返済することが出来るかを見る指数として有効です。
具体的には有利子負債を[経常利益-法人税等+減価償却費]で割ります。そうすると何年で借入金を返せるかが算定できます。有利子負債というのは簡単に言えば銀行からの借入金です。利息を払わない社長からの借入金は含まれません。経常利益は特別利益や特別損失を考慮しないところの利益です。別の言い方をすると売上高から売上原価と販売費および一般管理費を引いて営業外利益を足して営業外損失を引いたものです。その金額から法人税等の税金を引いて減価償却費を足します。これで出た金額を銀行借入金から割るというわけです。
最終的に出た数値の単位は年になります。この数値は少ない方が良くて(まだ借入金を借りられる余力があるということ)10年以内が望ましいと言われています。決算書をみれば算定することが出来ますので皆さんの会社の債務償還年数も何年か調べてみて下さい。この算式で良く聞かれるのが経常利益から税金を引くのは分かります。でもなんで減価償却費を足すのですか?という質問です。減価償却費を足すのは減価償却費は現金支出が伴わない費用だからです。何年で返せるかというのは会社がキャッシュフローで何年で返せるかを考えるので減価償却費のような現金支出を伴わない費用は経常利益を求めた時点で引かれてしまっているので、足してあげてキャッシュフローベースにするのです。